最近、ニュースやSNSで中国の国防動員法やその域外適用という言葉をよく耳にするようになりました。
特にビジネスで海外と関わりがある方や、これからの国際情勢がどうなるのか不安に感じている方にとって、中国の法律が日本の企業や私たちの生活にどう影響するのかという点は、避けては通れない関心事ですよね。
国防動員法の域外適用について調べると、内容が難しかったり、極端な意見が多かったりして、結局どういうことなのか分かりやすく知りたいと感じている方も多いはずです。
この記事では、中国の法律が国境を越えてどのような力を持ちうるのか、柔軟かつフラットに整理しました。読後の皆さんが、冷静に現状を把握できるようなヒントをお届けできれば幸いです。
国防動員法の域外適用:法的枠組みと構造
まずは、中国が構築してきた安全保障に関する法的な土台について見ていきましょう。
一見すると中国国内の法律のように見えますが、その影響力がどのように国境を越えていくのか、その構造を深掘りして紐解いていきます。
私たちが日常的に耳にする「有事」という言葉が、法的にどのような強制力を伴うのかを理解することが最初の一歩です。
国防動員法と域外適用の基本的な定義

「国防動員法」とは、2010年に施行された中国の基本法で、国家の主権や領土保全を守るために、平時から有事にかけての人員や物資の動員を準備・実施することを目的としています。
これだけ聞くと、多くの国にある「国家総動員体制」の法整備の一つに思えるかもしれません。しかし、この法律を語る上で欠かせないのが「域外適用」という考え方です。
一般的に、法律はその国の領土内でのみ有効ですが、域外適用とは「領土の外にいる人や組織に対しても自国の法律を適用する」ことを指します。
国防動員法には「全世界で適用する」という明文規定があるわけではありません。しかし、中国法が採用している「属人主義*1(Nationality Principle)」という考え方が、実質的な域外適用の根拠となっているのです。
これは、中国籍を持つ個人や、中国資本が支配する企業であれば、たとえ日本や米国にいたとしても、中国本国の法律や動員命令に従う義務があるという解釈です。
この解釈に基づけば、有事の際に日本で活動する中国系企業の現地法人が、中国政府の命令によって物流を停止させたり、保有する情報を本国に提供したりすることが、法的な「義務」として課される可能性が出てきます。
これは国際法における「属地主義*2(その土地の法律に従う)」と矛盾することが多く、グローバルビジネスを展開する上で非常に複雑かつ深刻な対立を生む要因となっています。
私たちが「他国の法律だから関係ない」と言い切れないのは、経済が高度に連結している現代において、この属人主義的な強制力がサプライチェーンを通じて間接的に日本国内にまで入り込んでくるからです。
*2 属地主義:法の適用範囲を行政区画内(領土内)に限定する法原則。国際的な管轄権争いでは、この原則と属人主義が衝突することが多い。
中国の安全保障法制が歩んだ歴史的な変遷

中国の安全保障法制は、決して唐突に現在の形になったわけではありません。数十年かけて、徐々にその網を広げてきた歴史があります。
1997年の国防法制定がその出発点と言えるでしょう。当時はまだ、主に「領土の防衛」に主眼が置かれていました。しかし、2010年に「国防動員法」が制定されたことで、民間のリソースをどのように軍事的に活用するかという具体的な「動員メカニズム」が定義されました。
さらに2015年には、包括的な「国家安全法」が制定されました。ここでは、伝統的な軍事だけでなく、経済、文化、金融、ネット空間、さらには深海や宇宙までもが安全保障の対象として定義されました。
続く2017年の「国家情報法」では、国民の情報提供義務が明文化され、平時からの監視・協力体制が強化されました。
そして、2020年の国防法改正により、防衛対象に「発展の利益*3」が追加されたことは、歴史的な転換点です。これにより、中国は「自国の経済発展を妨げる事象」に対しても、法的に国防動員を発令できる口実を手に入れました。
この歴史的な変遷を振り返ると、中国の安全保障の概念が「守り」から「拡張」へとシフトしてきたことが見て取れます。あわせて『存立危機事態と台湾の反応から読み解く2026年日本の安全保障と経済影響』も読むと、背景がより立体的に理解できます。
2026年現在、これらの法律は単なる規定として存在するだけでなく、実際の軍事演習や経済的威圧*4の場面で、その法的根拠として頻繁に参照されるようになっています。過去の法律が積み重なり、現在の巨大な安全保障システムを形成しているのです。
私たちが向き合っているのは、一点の法律ではなく、このように重層的に構築された巨大な法的アーキテクチャであるという認識を持つ必要があります。
*4 経済的威圧:貿易上の優位性を背景に、相手国の政策変更を迫る非軍事的な圧力。中国の安全保障法制はこの威圧を法的に正当化する側面を持つ。
国防動員法の内容をわかりやすく体系的に解説

国防動員法の全体像を把握するために、その主な内容を体系的に整理してみましょう。
この法律は、単に「戦争が起きたら兵士を集める」というだけのものではありません。平時からの準備が非常に綿密に設計されています。
1. 平時の準備と資源の把握
国は、有事に活用できる民間の資産(車両、船舶、航空機、建設機械など)を平時から把握し、登録させる権限を持っています。
また、「戦略物資」の備蓄制度を確立し、必要に応じて民間企業に備蓄を求めることができます。これには、エネルギーや食料だけでなく、半導体などの重要技術も含まれます。
2. 有事の徴用と補償
動員令が発動されると、国は登録された民間資産を強制的に徴用できます。法律上は「適切な補償を行う」とされていますが、戦時下においてその補償がどこまで実効性を持つかは不透明です。
特に、軍事調達契約を受けている企業や、国防に関連する研究を行っている単位は、最優先で軍の要求に応える義務を負います。これが先ほど触れた「第54条」の規定です。
3. 国民の動員義務
18歳から60歳の男性、18歳から55歳の女性は、国防動員の対象となり得ます。これには民兵*5としての活動や、後方支援任務などが含まれます。
この義務も「中国公民」であれば適用されるため、海外在住者への影響が議論されるポイントとなります。
体系的理解のポイント
- 主体:中国国内の組織・個人だけでなく、海外の中国籍主体も含む。
- 対象:人的リソース、物的リソース、さらにはデジタル・情報リソース。
- 発動条件:主権への侵害だけでなく「発展の利益」の侵害も含む。
このように、国防動員法は社会のあらゆる側面を「戦時モード」に切り替えるためのマスターキーのような役割を果たしています。
ビジネスの現場では、特に「第54条」に基づく優先供給義務が、他国企業との契約違反を引き起こすリスクとして警戒されています。
例えるなら、「学校で運動会をするときに、近所の家から勝手にトラックやテントを借りて、家族総出で手伝わせることを、あらかじめ法律で決めてある状態」に近いと言えます。ただし、その「近所」の範囲が、今や世界中に広がっているのがこの法律の最大の特徴です。
国家情報法との連携で強まる域外適用の実効性

国防動員法を「ハード面」の動員とするならば、2017年の「国家情報法」は「ソフト面」、つまり情報の動員を担う法律です。
この二つの法律が連携することで、域外適用はより強力な実効性を持つようになります。特に有名なのが第7条で、いかなる組織や個人も国家の情報活動に協力し、知り得た秘密を守らなければならないと定めています。
なぜこれが国防動員法と関係があるのでしょうか。それは、「有事の動員を成功させるためには、正確な情報が不可欠だから」です。
例えば、中国政府がある国の港湾施設を徴用、あるいは利用したいと考えた場合、その港の正確な深度、クレーンの性能、運用システム、警備体制などの情報を平時から把握しておく必要があります。
国家情報法に基づき、その港の管理に関わっている中国系企業や技術者から情報を収集しておけば、国防動員法を発動した瞬間に、即座にその施設を軍事的に活用することが可能になります。
また、この情報協力義務には地理的な制限がありません。中国の当局者によれば「法に従って活動する」ことが前提ですが、何が法にかなうかは当局の判断次第です。
これにより、海外のITインフラやネットワークを介して流れるデータが、安全保障の目的で収集される懸念が世界中で高まりました。
実際に米国や欧州、および日本でも、通信機器の排除やデータローカライゼーション*6(データの国内保存義務)の動きが加速したのは、この国家情報法の域外適用リスクを警戒した結果です。
平時の情報収集が、将来の国防動員のための「下調べ」として機能するという構造を理解することが、現代の安全保障リスクを考える上で極めて重要です。
2020年の国防法改正による動員範囲の拡大

2020年12月に行われた国防法の大規模な改正は、中国の国家戦略が大きな転換点を迎えたことを象徴しています。
それまでの国防法は、あくまで「外敵からの侵略を防ぎ、領土を守る」という防衛的な性格が強かったのですが、改正後はその適用範囲が大幅に拡張されました。
キーワードは、やはり「発展の利益(Development Interests)」の追加です。
この「発展の利益」には明確な定義がありません。一般的には、中国企業の海外活動、エネルギー資源の確保、重要なシーレーンの安全、サイバー空間や宇宙での優位性などが含まれると考えられています。
つまり、「中国が経済的に成長するために必要な要素」が脅かされた場合、それは国防上の危機であると認定し、軍を動かしたり、国民や企業を動員したりすることができるようになったのです。
例えば、他国が中国に対してハイテク製品の禁輸措置をとった場合、中国はこれを「発展の利益への重大な侵害」とみなし、国防動員法を発動して対抗措置をとる、というロジックが成立し得ます。
これは、経済摩擦や外交問題を、即座に「国防事態」へとエスカレートさせる法的回路が完成したことを意味します。
また、改正法では「海外の中国公民、組織、施設の安全を守る」という規定も強化されました。一見すると自国民の保護ですが、これを理由に他国の主権領域内で軍事活動や警察活動を行う根拠とされるリスクも指摘されています。
この「発展の利益」という言葉がどのように解釈されるかは、国際社会にとって最大の不透明要素の一つとなっています。法律が地理的な境界を越えるための「マジックワード」として機能しているのが現状です。
属人主義に基づく海外公民への法的義務
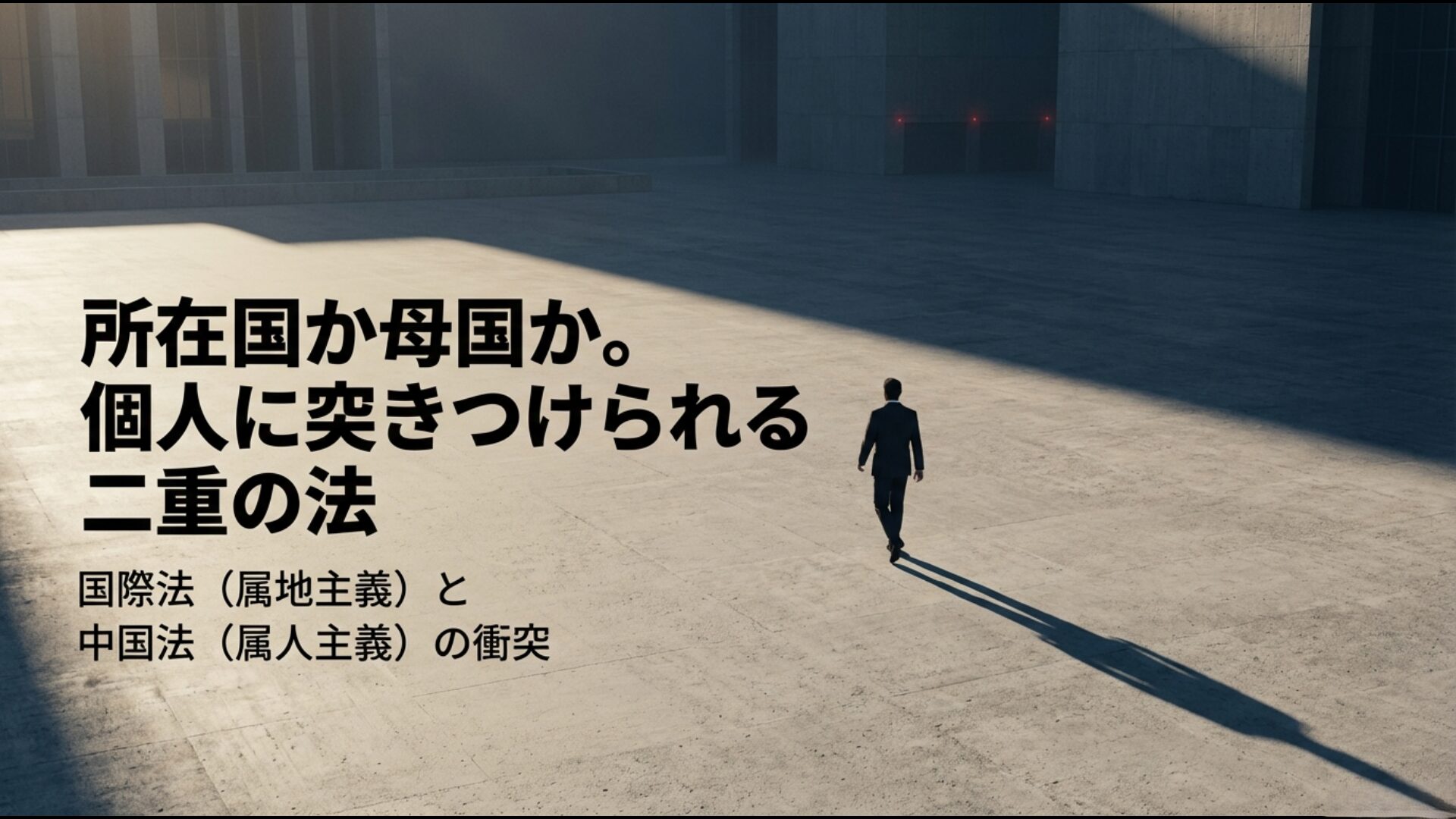
中国の法制度において、海外に住む中国籍の人々に最も重くのしかかるのが「属人主義」の問題です。
国際法では通常、滞在している国の法律に従う「属地主義」が優先されますが、中国は自国民に対して、場所を問わず自国の法律を守るよう求めています。
これは、海外に住む数千万人の華僑や華人、留学生、ビジネスマンにとって、所在国と母国の間で深刻な忠誠の葛藤を生じさせる原因となっています。
国防動員法に基づき、有事に帰国命令や現地での任務付与が出された場合、彼らはどうなるでしょうか。物理的に海外にいる彼らを直接罰することは難しいように見えます。
しかし、中国国内に残された家族への圧力、国内資産の没収、帰国時の拘束といったリスクが、実質的な強制力として機能します。
これは単なる理論上の話ではなく、過去には海外にいる活動家やその親族に対して、本国の法執行機関が様々な形で「働きかけ」を行った事例が報告されています。
また、企業の従業員についても同様です。中国系多国籍企業に勤務する中国人社員が、国家情報法や国防動員法に基づく命令を受けた場合、彼らは企業人としての倫理や現地の法律よりも、本国からの命令を優先せざるを得ない状況に追い込まれる可能性があります。
これは個人を責める問題ではなく、そのような過酷な法的状況を国家が作り出しているというシステムの問題です。
日本企業が中国人材を採用したり、協働したりする際には、この「法的な二重拘束*7」のリスクを正しく理解し、個人を保護しつつも情報の安全性を確保するという難しいバランス感覚が求められています。
軍民融合戦略がもたらす民間リソースの動員
「軍民融合(Military-Civil Fusion: MCF)」は、習近平政権が最優先課題として掲げる国家戦略です。これは、民間経済の成長と軍事力の近代化を一体化させ、互いに促進し合うことを目指しています。
国防動員法は、この軍民融合戦略を法的に担保する実行手段としての側面を持っています。この戦略により、平時の民間ビジネスの裏側に、常に軍事的な意図が組み込まれる構造が生まれました。
具体的な例として、物流と交通の分野を見てみましょう。2016年に施行された「国防交通法」は、国防動員法を補完する形で、民間の運送能力を軍事転用するための詳細なルールを定めています。
例えば、中国企業が建造する大型のフェリーやコンテナ船には、軍事輸送に適した設計(甲板の強化や車両用ランプの改修など)が義務付けられるケースがあります。これにより、有事の際には数千隻規模の民間船が、即座に軍の揚陸艦や補給艦として「動員」されることになります。
| 分野 | 平時の活動 | 有事の動員(軍民融合) |
|---|---|---|
| 海運・物流 | 世界各国の港湾運営、貨物輸送 | 軍艦の補給拠点、兵員輸送への転用 |
| 情報通信 | SNS運営、クラウドサービス提供 | サイバー攻撃、情報工作への協力 |
| 先端技術 | ドローンやAIの民生開発 | 兵器システムの高度化への技術転用 |
このように、民間の顔をした活動が、法的なトリガー一つで軍事活動に変貌する仕組みが「軍民融合」です。
これは域外においても同様で、中国企業が管理する海外の港湾が、有事には中国海軍の拠点として機能するのではないかという懸念(真珠の首飾り戦略*8)の根拠となっています。
民間リソースの境界線が消失していることが、国防動員法の域外リスクをより一層複雑なものにしています。
国防動員法の域外適用が日本企業に与えるリスク
ここからは、私たち日本や日系企業にとって、この法律が具体的にどのようなリスクをもたらすのかを掘り下げていきます。
特にビジネスの継続性(BCP)の観点から、知っておくべき現実的なシナリオがいくつかあります。感情的な議論ではなく、冷静な実務の観点からリスクを評価していきましょう。
日本企業が直面するリスクと地政学的背景
日本は、中国にとって最大の貿易相手国の一つであると同時に、軍事的には米国の同盟国であり、地理的には台湾海峡のすぐ隣に位置しています。この「経済的密接さ」と「政治・軍事的な対立」の板挟みになっているのが、現在の日本の状況です。
そのため、中国の国防動員法に関連する法執行が行われた際、その影響を世界で最も直接的に受けるのが日本企業だと言っても過言ではありません。
近年、日系企業の間ではリスク分散を目的としたチャイナ・プラス・ワン*9という動きが広がってきましたが、それでも依然として中国市場や中国製部品への依存度は高いままです。
米中対立が深まり、米国が中国に対して厳しい輸出規制をかければ、中国側も対抗措置として自国の安全保障法制を振りかざします。この「法律戦」の戦場に、日本企業は意図せずとも立たされているのです。
経営陣にとっては、単なるコスト削減や市場拡大だけでなく、経営リスクのトップ項目に据えなければならない時代になっています。
2026年現在、多くの企業がサプライチェーンの再構築を急いでいますが、それでもなお、この巨大なリスクを完全に回避することは容易ではありません。
最新の外交情勢については、公的な情報も常に確認しておく必要があります。(出典:外務省『中国:外交・安全保障』)
*10 地政学的リスク:地理的な位置関係や特定地域の政治・軍事的緊張が、経済やビジネスに悪影響を及ぼす不確実性。国防動員法の域外適用はその代表格と言える。
有事における在中資産の徴用と凍結の可能性

万が一、台湾情勢などが武力衝突に発展するような事態になった際、国防動員法は文字通りフル稼働することになります。このとき、中国国内にある日系企業の現地法人は、法的には「中国の組織」として扱われます。
したがって、国防動員法に基づき、工場の設備や在庫、資金、さらにはそこで働く従業員の動員までもが命令されるリスクが現実のものとなります。これは私たちが「自分の会社のものだ」と思っている資産が、瞬時に国家のアセットへと切り替わるプロセスです。
これに加え、現地の経営者が当局に拘束されるといった、いわゆる人質司法*11のリスクも併せて考慮する必要があります。
想定される資産リスク
- 敵性資産としての没収:日本が有事に何らかの形で関与した場合、日本企業の資産は「敵国の資産」とみなされ、強制的に没収・凍結される可能性があります。
- 強制的な軍需生産:民生用の製品を作っていたラインが、軍の命令により軍用部品や救援物資の生産に切り替えられる命令を受ける。
- 知的財産の接収:有事の「緊急事態」を理由に、企業が持つ機密技術やデータが、国防のために強制的に開示・利用される。
こうした事態において、現地法人が本国の日本本社の指示を仰ぐ余裕があるかは極めて疑わしいと言わざるを得ません。一度没収された資産を取り戻すことは、国際的な裁判を通じても極めて困難です。
そのため、事前に「どれだけの資産が徴用されても、本社が倒産しないか」という最悪のシナリオに基づいた耐性テストを行う企業が増えています。これは単なる悲観論ではなく、法的根拠に基づいた合理的な備えなのです。
台湾有事の発生時に懸念される物流の遮断

台湾海峡周辺は、日本のエネルギー供給や貿易の要衝であるシーレーン*12です。国防動員法が域外に及ぼす影響として最も恐ろしいのが、この海域における物流の完全な麻痺です。
中国が国防動員を発令すれば、世界中に散らばっている中国籍のコンテナ船、バルク船、および数万隻規模の漁船に対して、「直ちに指定の海域に集結せよ」あるいは「特定の航路を封鎖せよ」といった命令が出される可能性があります。
民間船が軍の指揮下に入ることで、通常の商流は完全に止まり、日本が必要とする原材料が届かず、製品も出荷できないという事態が数週間、あるいは数ヶ月続く可能性があります。
さらに、中国企業が運営権を持つ海外の港湾で、日本関係の荷物が差し止められたり、優先順位を下げられたりする「サイレントな動員」も想定されます。
これは物理的な破壊を伴わない経済的な兵糧攻めとしての側面を持っており、資源を海外に頼る日本にとっては武力攻撃と同等、あるいはそれ以上の脅威となります。
私たちが普段手に取っている製品の部品一つ一つが、こうした法的な動員リスクの網の中に組み込まれているという現実に、もっと自覚的にならなければなりません。
2024年以降、頻繁に行われている台湾周辺での軍事演習において、民間船の動員がシミュレートされている事実は、このリスクが現実の計画であることを裏付けています。
関連記事:台湾有事で危ない県はどこ?基地・原発リスクと避難先を徹底解説
反外国制裁法による法的ジレンマへの対応
日本企業が最も頭を悩ませているのが、2021年に制定された「反外国制裁法」への対応です。これは、米国などが中国に対して課す制裁措置に従うことを「中国の国益を損なう行為」として禁止する法律です。
ここには、国防動員法的な「国家への協力」という側面が色濃く反映されており、企業を法的なダブルバインド*13へと追い込みます。
| 企業の行動 | 米国側の反応 | 中国側の反応 |
|---|---|---|
| 米国の輸出規制に従う | 法令遵守(安全) | 反外国制裁法違反(罰則・資産没収) |
| 中国への配慮で規制を回避 | 制裁逃れ(巨額罰金・ドル決済禁止) | 法令遵守(安全) |
このように、日本企業は「あちらを立てればこちらが立たず」という、極めて過酷なダブルバインド(二重拘束)の状態に置かれます。
もし米国法を守れば中国で処罰され、中国法を守れば米国からグローバルな経済圏から追放されるというリスクです。これは企業の努力だけで解決できる問題ではなく、政府レベルでの外交的な保護や、法的なガードレールの構築が不可欠です。
しかし、現状では各企業が自力で、どちらの法リスクがより致命的かを測りながら、細い糸の上を歩くような経営を強いられています。国防動員法的な考え方が背景にある以上、中国側は「我が国の利益を損なう者は、敵対的行為を行っているとみなす」という強い姿勢を崩さないでしょう。
国家安全法を含む包括的な安全保障リスク
国防動員法は、それ単体で機能するのではなく、他の多くの安全保障法制と有機的に結びついています。
2015年の国家安全法、2021年のデータ安全法、および2023年に大幅に強化された「反スパイ法」などがそれです。これらの法律に共通するのは、「国家安全」の定義が極めて曖昧で、当局の裁量でいくらでも広げられるという点です。
例えば、ある企業が中国市場で成功するために行った緻密な市場データ収集や、現地のパートナー企業との技術提携が、ある日突然「国家安全に関わる情報を不当に取得した」として反スパイ法の対象になるかもしれません。
スパイ行為の境界線については、別記事『スパイ防止法のメリットとデメリットを徹底解説!2026年最新の動向』で詳しくまとめています。
あるいは、中国国内のサーバーに保存しているデータが、データ安全法を根拠に当局への提出を求められることもあります。
これらは平時から行われるものですが、ひとたび国防動員法が発動されるような事態になれば、これらの法制度によって集められたデータや人脈が、一気に「攻撃」や「統制」のためのリソースへと反転します。
私たちが注意すべきは、「平時」だと思っている今の活動が、法的には既に「有事」への準備として組み込まれている可能性があるという点です。透明性の欠如こそが、最大のリスクと言えるでしょう。
よくある質問(FAQ)
国防動員法 域外適用への備えと今後の展望

ここまで見てきた通り、国防動員法 域外適用のリスクは、単なる他国の法律の話ではなく、日本の経済、企業の存立、および私たちの生活に直結する課題です。
2026年現在、私たちはもはや「リスクがない」世界には戻れません。重要なのは、リスクを正しく評価し、それに対してどのような耐性を持てるかという「レジリエンス(回復力)」の構築です。
特定の思想に偏ることなく、事実を積み上げて、冷静に対策を練る必要があります。
これからのリスクマネジメントの指針
- デリスキングの徹底:完全に中国を切り離す(デカップリング)のは難しくても、重要部品の代替調達先を確保するなど、依存度を下げる「デリスキング」は必須です。
- 法務・ガバナンスの再構築:中国の法律がどのように自社に影響するか、現地の法律事務所だけでなく、第三国(米国や欧州)の視点も含めた多角的な法的チェックを行ってください。
- 情報のローカライゼーション(逆適用):中国に関する機密情報は中国外に、中国拠点のデータは物理的に他拠点と分離するなど、データ保護の壁を厚くしてください。
こうした国際情勢は非常に複雑で、一筋縄ではいきません。この記事で提供した情報はあくまで一つの視点であり、具体的なビジネス判断を行う際には、必ず外務省や経済産業省、ジェトロ(日本貿易振興機構)といった公的な機関の最新情報を参照してください。
(出典:独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)『中国・安全保障関連法制の動向』)
また、個別の事案については国際法務や安全保障の専門家に相談されることを強くお勧めします。世界が激変する中で、私たちは「知ること」を武器にして、自分たちの生活と経済を守っていかなければなりません。この記事が、皆さんの思考を深める一助となれば幸いです。
※この記事に記載された数値データや法解釈は、公開されている情報を基にした一般的な目安であり、2026年時点の情勢を反映していますが、将来の法改正や運用変更、特定の事案に対する法的助言を保証するものではありません。最終的な判断は読者自身の責任において行い、必ず専門家へご相談ください。


