普段、テレビや新聞のニュースを眺めていて、ふと違和感を覚えることはありませんか。
ネットで流れている一次情報やSNSでの反応と、大手メディアが報じる内容があまりに乖離しているのを見ると、「オールドメディアはなぜ偏向報道をするのか」という疑問が湧いてくるのは、今の時代とても自然なことだと思います。
そもそもオールドメディアの意味とは具体的に何を指すのか、そしてなぜこれほどまでに信頼性が揺らいでいるのか。
過去の偏向報道の事例やメディアが信用できないと言われる背景には、私たちが想像する以上に複雑な歴史や業界の構造が隠されています。
この記事では、ニュースの裏側にある仕組みを整理し、私たちが情報に踊らされないためのメディアリテラシーについて一緒に考えていければと思います。
オールドメディアでなぜ偏向報道が起きるのか
テレビや新聞といった伝統的なメディアが、なぜ特定の方向に偏った情報を流してしまうのか。
その理由は、現場の記者の個人的な考えだけでなく、日本のメディア業界が抱える「仕組み」そのものに原因があるようです。
まずは、その構造的な背景から紐解いていきましょう。
オールドメディアの定義と役割の変遷

「オールドメディア」という言葉を私たちが日常的に使うとき、そこには単なる「古い媒体」以上のニュアンスが含まれているように感じます。
一般的には、新聞、テレビ、ラジオ、雑誌といった、インターネットが普及する以前から情報を独占してきた既存の巨大メディアを指します。
かつてこれらのメディアは、社会で何が起きているかを決定し、国民に伝える「情報のゲートキーパー*1(門番)」として絶大な権威を誇っていました。
しかし、2020年代に入り、情報の流れは劇的に変化しました。SNSやYouTubeなどのニューメディアが台頭し、誰もが情報発信者になれる時代が到来したことで、オールドメディアが守ってきた「情報の独占権」は完全に崩壊しました。
かつてはメディアが報じなければ「なかったこと」にされていた事実が、今ではネットを通じて瞬時に拡散されます。この変化の中で、メディア側が従来の「エリート意識」や「世論を導く」という特権的な姿勢を崩さないことが、ユーザーとの間に大きな溝を生んでいます。
現在の検索トレンドを見ても、多くの人が「オールドメディア 意味」と調べると同時に、既存メディアに対する「既得権益」や「時代遅れ」といった不満を抱いています。
メディアの役割は、今や「情報を与える側」から、膨大な情報の中から「真偽を検証する側」へと変わるべき時期に来ていますが、そのアップデートが追いついていない現実が、今の強い違和感に繋がっているのではないでしょうか。
戦後メディア史が報道姿勢に与えた影響

日本のメディアがなぜ特定の思想に偏りやすいのか、そのルーツを辿ると戦後直後の混乱期にまで遡ります。
戦時中、日本の新聞や放送は、軍部と一体となって「国民の戦意高揚」を図る役割を担っていました。しかし、1945年の敗戦を境に、彼らは180度の転換を迫られます。
GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)による指導の下、昨日の軍国主義から今日の民主主義へと、文字通り「一晩で」論調を入れ替えたのです。
この劇的な転向は、メディア内部に深いトラウマと独自のアイデンティティを生みました。
それは、「国家権力は常に暴走する可能性があるため、メディアは常に権力の監視者(批判者)でなければならない」という強固な自己定義です。
この姿勢自体はジャーナリズムとして正当なものですが、日本ではこれが極端な形で定着しました。つまり、「政府のやることに反対することこそが正義である」という硬直化したバイアスを生んでしまった側面があるのです。
さらに、1955年体制*2と呼ばれる自民党の長期政権下で、万年野党化した社会党などの勢力に代わり、リベラル系の新聞やテレビが「書く野党」としての役割を自認するようになりました。
これにより、客観的な事実報道よりも、政権を批判するための「アングル(切り口)」が優先される土壌が形成されていきました。私たちが感じる「偏り」の多くは、この戦後から続くメディア独自の「正義感」に端を発していると考えられます。
クロスオーナーシップによる言論の固定化
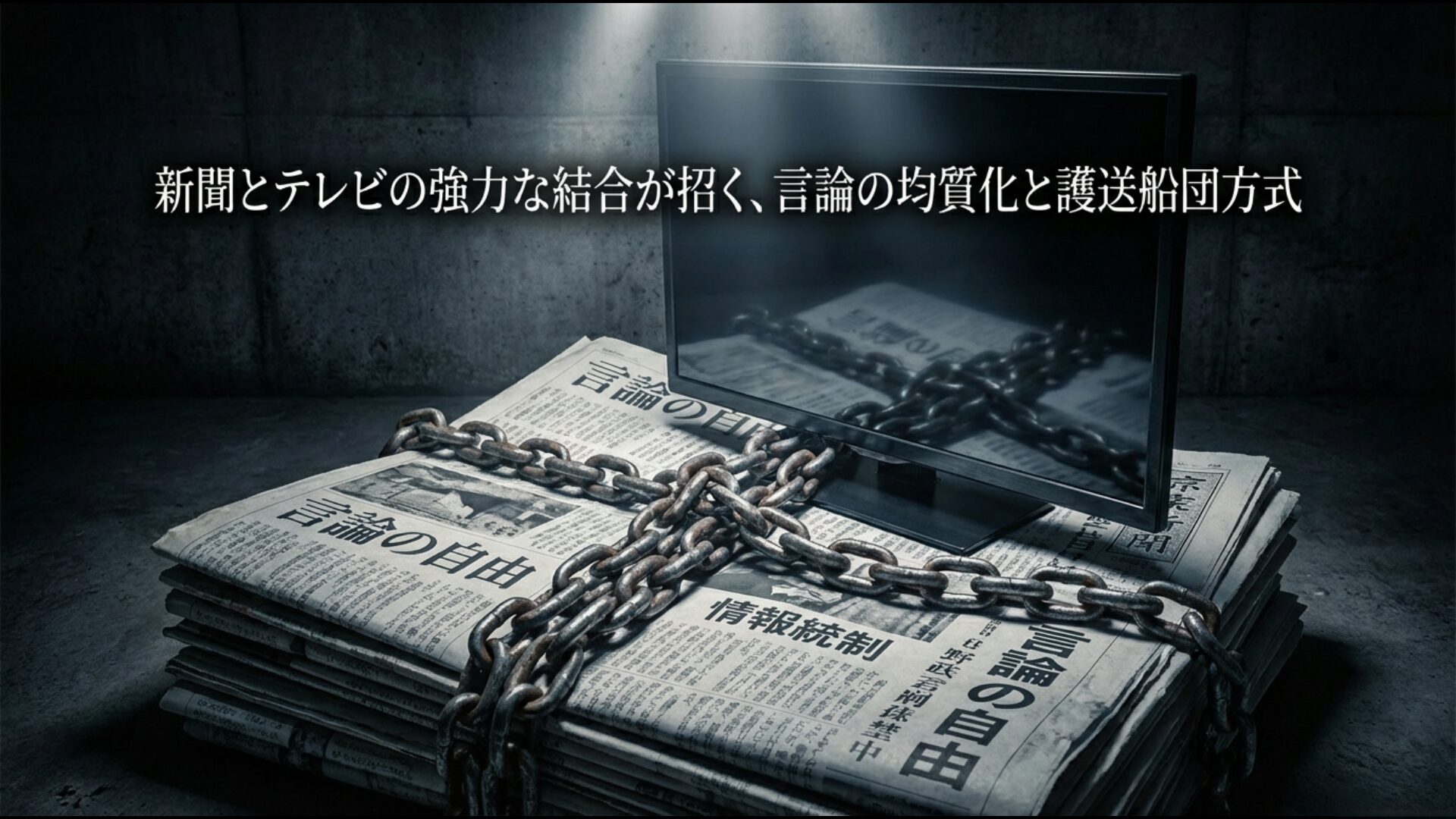
日本のメディア環境を理解する上で、最も重要な構造的問題が「クロスオーナーシップ」です。
これは、新聞社が放送局(テレビ局)を系列下に持ち、資本的にも人的にも密接に結びついている状態を指します。
世界的に見ても、日本のように全国紙とキー局がこれほど強固にペアを組んでいる例は非常に珍しいものです。
| 主要新聞社 | 系列テレビ局 | 主な傾向 |
|---|---|---|
| 読売新聞 | 日本テレビ | 保守・中道寄り |
| 朝日新聞 | テレビ朝日 | リベラル・左派寄り |
| 毎日新聞 | TBSテレビ | 中道・リベラル寄り |
| 日本経済新聞 | テレビ東京 | 経済重視 |
| 産経新聞 | フジテレビ | 保守・右派寄り |
この仕組みの最大の問題点は、「言論の多様性が失われる」ことです。
親会社である新聞社の社説や意向が、系列テレビ局のニュース番組のトーンに大きく反映されます。また、新聞が優遇されている「再販制度*3」などの業界特有の利権について、系列のテレビ局が批判的に報じることはまずありません。
メディア同士が互いを批判し合う「相互監視」が機能せず、結果として業界全体が一つの巨大な「護送船団」のように振る舞い、情報の均質化を招いているのです。
記者クラブ制度とアクセスジャーナリズム

日本のニュースがどれを見ても似たり寄ったりな内容になる背景には、独特の「記者クラブ制度」が存在します。
これは、官公庁、警察、政党などの主要機関に設置された専用の取材拠点であり、そこに所属できるのは大手メディアの記者のみという極めて閉鎖的なギルド社会です。フリーランスやネットメディアの参入は厳しく制限されており、情報の入り口が一部の組織に独占されています。
この制度下では、当局からの公式発表をそのまま報じる「発表ジャーナリズム」が横行します。記者はクラブ内にいれば自動的に情報が手に入るため、足を使った独自の調査報道*4を行うインセンティブ(動機)が働きにくくなります。
さらに、取材対象(官僚や政治家)と日常的に接することで、人間関係が密になりすぎる「アクセス・ジャーナリズム」の弊害が生まれます。相手に嫌われて取材ができなくなることを恐れ、厳しい追及を避けたり、特定の情報を意図的に伏せたりといった「忖度(そんたく)」が自然と発生してしまうのです。
このような「権力との馴れ合い」が、重要な情報の隠蔽や、都合の良い切り取り報道を助長し、国民が求める真実から遠ざかる一因となっているのは皮肉なことです。
情報の透明性を高めるためには、この閉鎖的な記者クラブという壁をいかに壊すかが長年の課題となっています。
電通やスポンサーの圧力が生む報道タブー

民放テレビ局は、視聴者からお金をもらっているわけではありません。
彼らの真の顧客は、広告を出してくれる「スポンサー企業」です。そして、そのスポンサーと放送局の間を繋ぐ強力なハブとなっているのが、日本最大の広告代理店である「電通」です。
この三角形の構造が、報道の自由を経済的な側面から縛り付けています。
広告収益モデルが抱えるリスク
- 大口スポンサーの不利益になる情報は報じにくい(例:原発、大手自動車メーカーの不祥事など)
- 電通が関わるイベントや国策事業に対して批判的な論陣を張りづらい
- 視聴率を優先するあまり、本質的なニュースよりも刺激的なスキャンダルを優先する
かつての福島第一原発事故以前、電力会社が莫大な広告費を各メディアに投下していたことで、原発の危険性を訴える声が封じ込められていた事実は、スポンサータブーの最たる例です。
メディアが「公器」を自称しながらも、実態は営利企業*5である以上、自分たちの首を絞めるような報道を控えてしまうのは避けられない構造的欠陥かもしれません。
私たちがニュースを見る際は、「この記事によって得をするスポンサーは誰か、逆に損をするのは誰か」という視点を持つことが不可欠です。
GHQのプレスコードと戦後メディアの転向
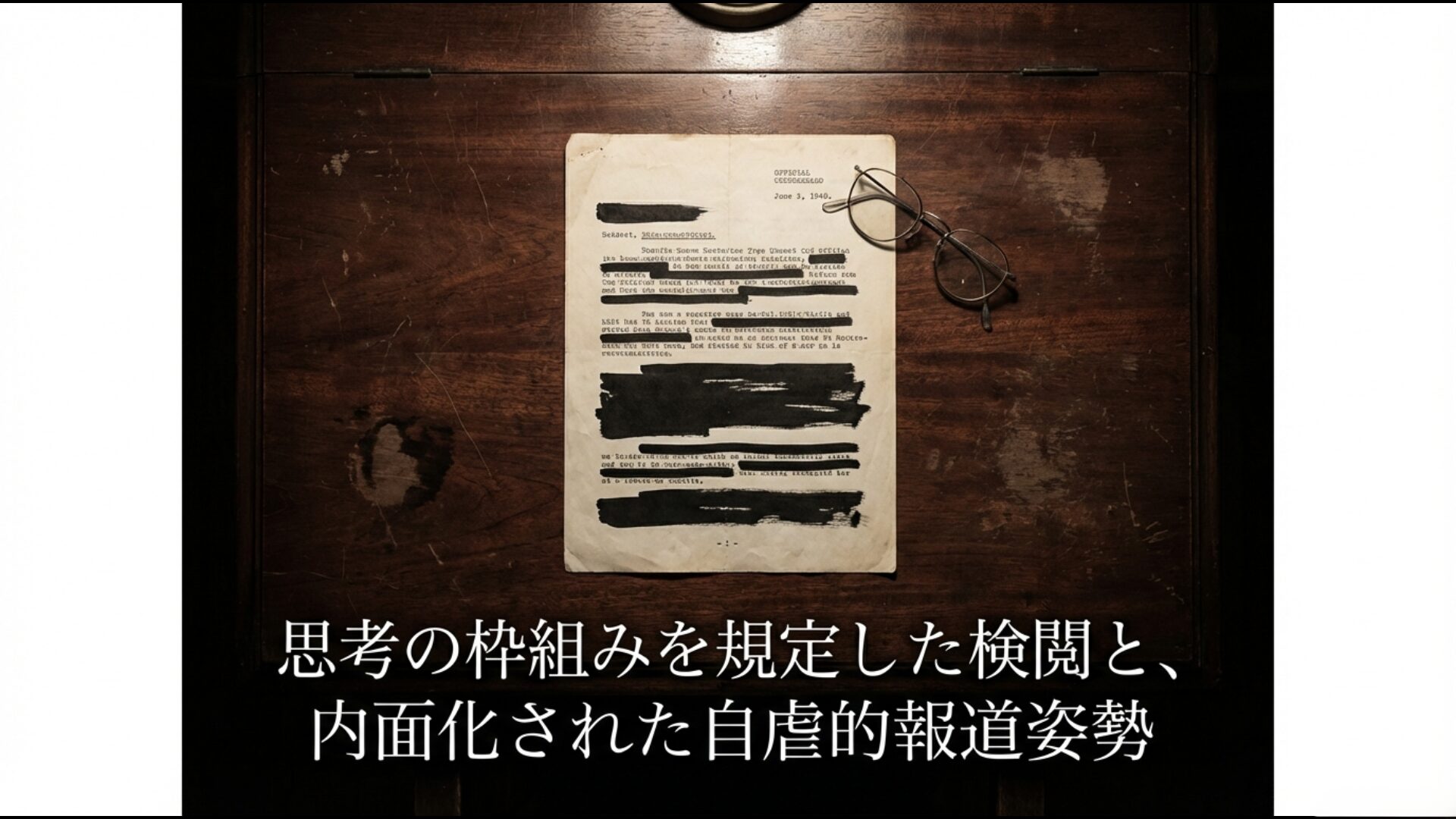
戦後メディアの根幹にある思想を理解するには、GHQが敷いた「プレスコード(新聞紙法)」について知らなければなりません。
1945年から1952年までの占領下において、日本のメディアはGHQによって厳格に検閲されていました。このコードには「連合国に対する批判」「占領軍に対する批判」に加え、「戦時中の日本軍を美化する表現」などが30項目にわたって禁止されていました。
この検閲の恐ろしかった点は、単に情報を消すだけでなく、「何が正しい考え方であるか」という思考の枠組みを強制的に規定したことにあります。
メディアは生き残るために、「戦前の日本=すべて悪」「連合国の持ち込んだ民主主義=絶対善」という二元論を積極的に内面化しました。
GHQがいなくなった後も、この「自主規制」の癖は残り続け、メディア内部の教育や人事を通じて継承されていきました。メディアのリベラル*6化が進んでいったと言えるでしょう。
これが現在において、「日本を肯定的に報じると右翼的と見なされる」といった、一見すると不自然なまでの自虐的・配慮的な報道姿勢の源流となっています。
オールドメディアはなぜ偏向報道をするのか:構造から紐解く
ここまで構造や歴史を見てきましたが、実際にどのような「事件」が起きて信頼が失われていったのでしょうか。具体的な事例や、現代のネット社会における反応から、メディアの現在地を確認してみましょう。
椿事件にみる政治的公平性の欠如と検証

日本の放送史を語る上で、信頼崩壊の分水嶺となったのが、1993年の「椿事件」です。
当時のテレビ朝日報道局長であった椿貞良氏が、民間放送連盟の会合で「自民党政権を倒して反自民の連立政権を成立させるために、特定の方向性の報道を行うよう指示した」と発言したことが発覚しました。
これは、メディアが中立の立場をかなぐり捨て、自らが「政治的な世論操作の主役」になろうとした衝撃的な出来事でした。
具体的には、選挙期間中に自民党幹部のマイナスイメージを植え付けるような編集を行ったり、特定の候補者を魅力的に見せるような演出を加えたりといった手法が取られたとされています。
この事件により、テレビ朝日は郵政省(当時)から放送免許取り消しの可能性すら示唆される厳重注意を受け、椿氏は国会に証人喚問*7されました。
この事件が私たちに教えるのは、「公共の電波を使っているメディアが、自分たちの思想を実現するために国民を洗脳し得る」という恐ろしい可能性です。
現在でも、選挙のたびに「放送時間が公平ではない」「特定の候補者ばかり取り上げられている」という批判がネット上で噴出しますが、その不信感の根底には、この椿事件の記憶が刻まれているのです。
放送法4条の撤廃をめぐる法的かつ政治的論点
放送法4条は、放送事業者に対して「政治的公平」を求めている非常に重要な条文です。
(出典:e-Gov法令検索『放送法』)
しかし、2018年頃から政府内でこの「4条撤廃」の議論が浮上しました。
その狙いは、インターネット放送などとの競争を促し、放送を自由化することにありました。もし撤廃されれば、日本でもアメリカのFOXニュースのように、特定の政治的立場を鮮明にした放送局が登場する可能性があります。
これに対し、メディア側は「報道の自由が守られなくなる」「権力が番組内容に介入する口実になる」として猛烈に反発しました。BPO*8という自律機関もあるとの主張です。
一方で、ネット上の世論や保守層からは、「現状でも4条が守られていないのだから、いっそ撤廃して『うちはこの立場です』と宣言した方が誠実だ」という皮肉めいた意見も多く見られました。
放送法4条の実態
放送法4条は、現在の日本では罰則規定のない「倫理規定」として運用されています。そのため、放送局が明らかに偏った報道をしたとしても、法的に免許が取り消されることは実質的にありません。この「形式上の公平」という盾が、逆にメディアが偏向批判から逃れるための「隠れみの」になっているという矛盾が生じているのです。
法改正の議論は現在停滞していますが、オールドメディアが「公平」を盾にし続けるのか、あるいは多様な意見の一つとして生き残るのか、その岐路に立たされているのは間違いありません。
外国勢力の影響や報道人のルーツ・国籍に関する疑念
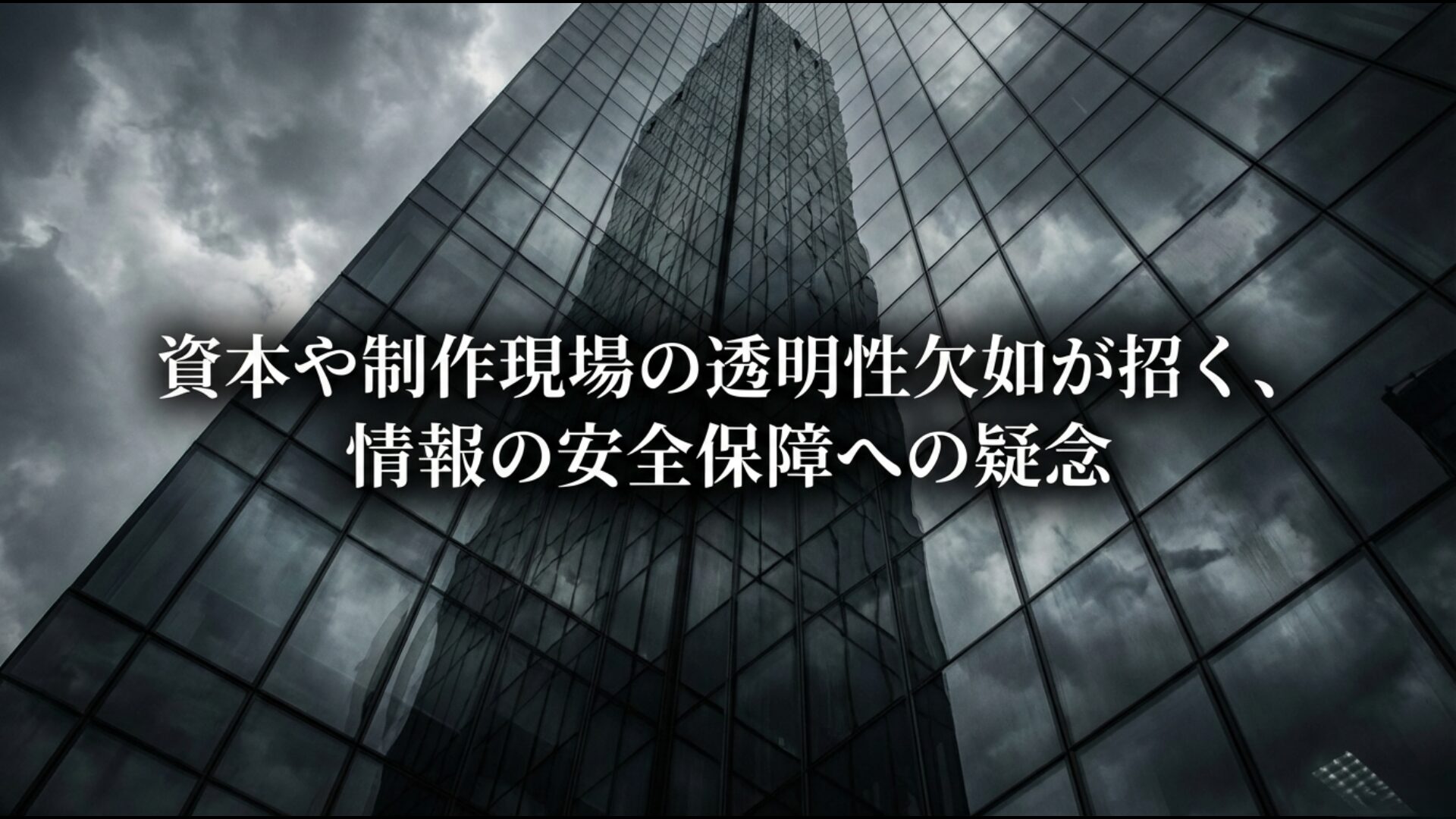
ネットで「偏向報道」について調べていると、よく「報道関係者に外国籍の人が多いのではないか」とか「特定の国の息がかかっているのではないか」といった、個人のルーツや国籍に関する疑念を耳にすることがあります。
これは非常にセンシティブな話題ですが、多くのユーザーが不信感を抱く大きな要因の一つになっているのは事実です。
まず、法的な側面から整理してみましょう。日本の放送法や電波法には、公共の電波が外国勢力に支配されるのを防ぐための「外資規制*9」というルールが存在します。
具体的には、テレビ局などの認定放送持株会社*10において、外国人が持つ議決権の割合を20%未満に抑えなければならないと定められています。
(出典:総務省『放送分野における外資規制』)
外資規制の重要性と過去の事例
この20%という数字は、日本の放送の自律性を守るための絶対的な防波堤です。しかし過去には、この外資比率がわずかに制限を超えていたことが後から発覚し、フジ・メディア・ホールディングスや東北新社などが大きな批判を浴位、一部で免許取り消し騒動にまで発展したケースもありました。こうした「うっかり」では済まされない管理の甘さが、視聴者に「裏で外国の資本が影響しているのではないか」という疑念を抱かせるきっかけとなっています。
また、資本の論理だけでなく、番組制作の現場における「人的な影響」についても議論が絶えません。
テレビ番組の多くは、局の社員だけでなく多くのアウトソーシング(制作会社)によって作られています。これらの現場で働く人たちの国籍やバックグラウンド、あるいは特定の国とのビジネス的な繋がりが、結果として「特定の国を優遇するような表現」や「日本を一方的に批判するようなアングル」を生んでいるのではないか、という指摘です。
特に近隣諸国との歴史問題や政治的対立において、メディアが日本側の主張よりも相手国の主張に寄り添っているように見えるとき、視聴者は「制作陣に特定の意図を持った勢力が入り込んでいるのではないか」という強い違和感を覚えます。
実際に、番組制作における海外プロダクションとの協力関係や、コンテンツの輸出入に伴う経済的な利害関係が、報道のトーンに影響を与える可能性は否定できません。
もちろん、個人の出自だけでその人の報道姿勢を決めつけるのは避けるべきですが、ニュースを作る側の「透明性」が確保されていないことが、今の深刻な不信感を招いている一因だと言えるでしょう。
私たちが情報を受け取る際は、そのニュースが「誰の資本で、どのような視点を持つ人たちによって作られたのか」という背景にまで想像力を働かせることが、これまで以上に重要になっています。
※情報の安全保障については、別記事『スパイ防止法のメリットとデメリットを徹底解説!2026年最新の動向』を参照してください。
*10 認定放送持株会社:傘下に複数の放送局を持つことができる持株会社制度。経営の効率化を目的とするが、公共性が高いため総務大臣による厳格な外資規制の監視対象となる。
マスゴミというネットスラングと信頼性の失墜

2000年代以降、ネット上で定着した「マスゴミ」という言葉は、もはや単なる悪口の域を超え、既存メディアに対する絶望感の象徴となっています。
かつてエリートの代名詞だった新聞記者やテレビマンが、なぜ「ゴミ」と呼ばれるまでになったのか。それは、彼らが国民に対して「上から目線」で教訓を垂れ流す一方で、自分たちの不祥事や間違いには甘く、特権階級のように振る舞う姿勢が可視化されたからです。
特にSNSの拡散力は、メディアの「ダブルスタンダード*11(二重基準)」を容赦なく暴き出します。
他人の不倫や失言には人格否定レベルの叩きを行う一方で、身内のテレビ局員の犯罪や捏造は小さく報じて済ませる。あるいは、地方の現状をバカにするような編集を行う。こうした「庶民感覚とのズレ」と「選民意識」が、ネットユーザーの怒りに火をつけました。
また、情報の裏取りを怠り、ネット上の誤情報をそのままニュースに流すといった「質の低下」も顕著です。「プロのジャーナリズム」を自称しながら、情報の精度でSNSの個人に負けているという現実。このプライドと実力の乖離こそが、「マスゴミ」という言葉に込められた深い蔑みの正体だと言えるでしょう。
信頼を失うのは一瞬ですが、それを取り戻すには、これまでの特権意識を捨てた真摯な姿勢が求められます。
メディアが嘘をつく理由と信用できない背景
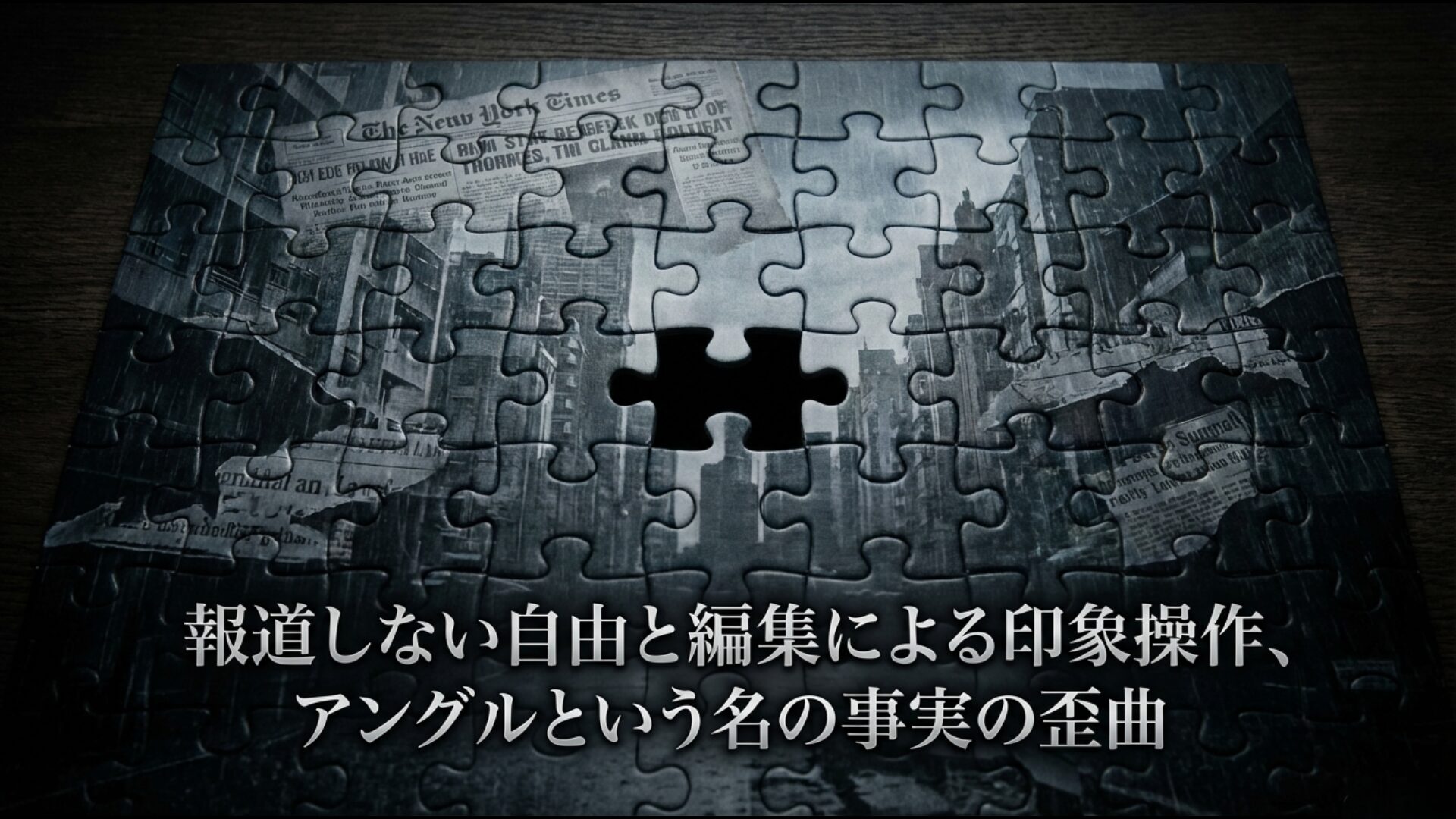
「メディアは嘘をつく」と言われるとき、そこには主に三つのパターンが存在します。
一つ目は単純な「誤報や捏造」ですが、これは発覚すれば大きな問題になるため頻度は低めです。
より巧妙で問題なのは、二つ目のパターン、すなわち「報道しない自由(情報の取捨選択)」です。ある事件のA面は大きく報じるが、自分たちの主張に不都合なB面は一切触れない。これだけで、視聴者の印象は完全に操作されてしまいます。
三つ目は「編集による印象操作」です。インタビューの一部を文脈と関係なく切り取ったり、街頭インタビューで自分たちの意図に沿った意見を言う人だけを採用したりする手法です。これは嘘をついているわけではありませんが、事実を歪めて伝えている点では嘘以上に悪質かもしれません。
| 手法 | 具体的内容 | 目的 |
|---|---|---|
| アジェンダ設定*12 | 特定の話題ばかりを連日報じる | 国民の関心を特定の方向に誘導する |
| チェリーピッキング | 都合の良いデータや意見だけを抽出 | 自分たちの論説を補強する |
| レッテル貼り | 「極右」「反日」などの刺激的な呼称 | 冷静な議論を封じ、感情的な対立を煽る |
メディアがこうした手法に頼る背景には、「自分たちは正しい情報を国民に教えてあげるべきだ」という誤ったパターナリズム*13(父権主義)があります。
しかし、今の私たちは、もう「教えられる側」ではありません。
複数の情報をクロスチェックし、メディアの隠した「B面」を自ら探しに行く。その姿勢が、騙されないための唯一の防波堤になります。
*13 パターナリズム:強い立場にある者が、弱い立場の者の利益のためとして干渉すること。メディアが国民を「教え導く対象」と見なし、一方的な価値観を押し付ける姿勢を指す。
よくある質問(FAQ)
総括:オールドメディアはなぜ偏向報道を行うのか
ここまで、オールドメディアにおいてなぜ偏向報道が生じるのか、その根深い原因を探ってきました。
私たちが向き合っているのは、特定の個人の悪意というよりも、半世紀以上にわたって積み上げられた「システムの疲弊」です。
💡 報道を歪ませる「4つの構造的要因」
- クロスオーナーシップ: 新聞と放送の資本一体系による多様性の喪失
- 記者クラブ制度: 情報源の独占と、発表内容の横並び化
- スポンサー依存: 広告主への忖度が生じやすい収益構造
- 戦後の呪縛: 歴史的背景からくる特定の思想的バイアス
大切なのは、メディアを完全に否定することではありません。「メディアは偏っているものだ」という前提を持って情報を消費する習慣を身につけることです。
どんなに優れたジャーナリストでも、完全な中立は不可能です。私たちは、彼らがどのようなフィルターを通して世界を見せようとしているのか、その「メガネの度数」を見極める知恵を持たなければなりません。
【実践】リテラシーを高める3つのアクション
一次情報の確認
SNS等で現場の生の声や元データにあたる
複数紙の読み比べ
対立する論調のメディアを比較してみる
海外視点の導入
外から見た「日本」の報じられ方を知る
情報は「与えられる恵み」ではなく、「勝ち取る権利」です。
誰かの意図で作られたストーリーに踊らされるのではなく、自らの力で本質を掴み取る。そんな「自立した情報消費者」が増えることこそが、メディアに対する最大の牽制となり、彼らを自浄作用へと向かわせる唯一の道だと信じています。
本記事の内容は、2026年現在の一般的な報道状況や歴史的経緯を個人の視点で整理したものです。報道に関する法規制や各社の指針は変更される場合があります。正確な情報は総務省の公式サイトや放送倫理・番組向上機構(BPO)の公開情報、各メディアの公式見解を併せてご確認ください。最終的な判断は、複数のソースを確認の上、ご自身の責任で行ってください。(出典:放送倫理・番組向上機構(BPO)公式サイト)


