アメリカの外交方針を語る上で欠かせない「モンロー主義」ですが、2026年1月、ベネズエラでの電撃的な軍事介入を機に、その言葉の重みがかつてないほど増しているように感じます。
そもそもモンロー主義の目的とは何なのか、そして今、トランプ氏が掲げる「ドンロー主義」とは。
この記事では、1823年の提唱当時の背景から、時代とともに変化してきた目的を整理してお伝えします。
現代の複雑な世界情勢を読み解くヒントにしていただければ幸いです。
- Pointモンロー主義が提唱された本来の目的
- Point歴史の中で盾から棍棒へ変質した過程
- Point2026年ベネズエラ介入による電撃的な変化
- Pointドンロー主義が日本や世界に及ぼす影響
- ✓米国の外交政策の歴史と現代の変化を知りたい
- ✓2026年ベネズエラ介入の国際的な影響を学びたい
- ✓日本の安全保障やエネルギー問題に関心がある
モンロー主義の目的と200年にわたる歴史的変遷
まずは、モンロー主義がどのようにして生まれ、アメリカの外交政策の根幹となっていったのか。その歴史的な基礎知識と背景から見ていきましょう。
モンロー主義の基本概念と定義をわかりやすく解説

モンロー主義とは、1823年に第5代アメリカ大統領ジェームズ・モンローが年次教書演説*1の中で示した外交上の指針です。
私たちがこの概念を理解しようとする際、まず押さえておくべきなのは、これが当時のアメリカにとっての「生存戦略」であったという点です。
19世紀初頭、アメリカはまだ独立から日が浅く、軍事的にも経済的にもヨーロッパ列強に太刀打ちできるレベルではありませんでした。そのような状況下で、自国の安全を確保するために打ち出されたのがこのドクトリン(信条)なのです。
この主義は、大きく分けて「三つの原則」で構成されています。
一つ目は「非植民地化」です。南北アメリカ大陸において、ヨーロッパ諸国が新しく植民地を作ることは認めないという宣言です。
二つ目は「不干渉」。ヨーロッパの国々がアメリカ大陸にある独立国の政治に口を出すことは、アメリカ合衆国への非友好的な行為(つまり、敵対行為)とみなす、という強い警告を含んでいました。
そして三つ目が「分離主義(二つの世界)」です。アメリカもヨーロッパの争いには関わらないし、今あるヨーロッパの植民地についてもとやかく言わない、という「お互いに不可侵でいよう」という約束事でした。
モンロー主義の核心:
「旧世界(ヨーロッパ)」と「新世界(アメリカ大陸)」を明確に区別し、それぞれの領域での主権*2を尊重し合うことで、アメリカ大陸における列強の影響力を排除しようとした。
この考え方は、当時のアメリカ国民に「自分たちはヨーロッパのしがらみから自由な、新しい価値観を持つ国なのだ」という強い自覚を植え付けることにもなりました。
単なる外交文書を超えて、アメリカのアイデンティティを形作るイデオロギー装置として機能したわけです。
私たちが「なぜアメリカは自国の近隣諸国に対してこれほどまでに敏感なのか」と疑問に思ったとき、その原点がこの1823年の宣言にあることを知ると、パズルのピースが埋まるような感覚になりますね。
■ 脚注解説:より深い理解のために
*1 年次教書演説:大統領が議会に対し、国家の現状を報告し政策指針を示す演説。重要な外交ドクトリンが国民や世界へ公式に表明される場となります。
*2 主権:国家が他国の干渉を受けず、自国の領土や国民を統治する最高の権利。近代国家の成立と国際秩序を支える根本的な法的概念です。
1823年の歴史的背景とドクトリンが提考された経緯

モンロー主義がなぜ1823年というタイミングで生まれたのか。その背景には、当時の世界を揺るがしていた巨大な政治的うねりがありました。
私たちが歴史を振り返るとき、この時代のアメリカは非常に危うい立場に立たされていたことがわかります。ナポレオン戦争*3が終結した後のヨーロッパでは、ロシア、オーストリア、プロイセンといった君主制の国々が「神聖同盟」*4を結成し、自由主義や民主主義の芽を摘み取ろうと躍起になっていました。
彼らの次のターゲットは、スペインの支配から抜け出そうとしていた中南米諸国でした。もしヨーロッパの軍隊が再びラテンアメリカに上陸し、かつての植民地支配を復活させてしまったら、アメリカ合衆国は再び列強に包囲されてしまう——。
モンロー大統領と、実質的な起草者であるジョン・クインシー・アダムズ国務長官は、この危機を回避するために先手を打つ必要があったのです。
ここで非常に面白い、そして皮肉な事実があります。
当時、アメリカにはこの宣言を武力で裏付けるだけの海軍力はほとんどありませんでした。実は、このドクトリンが実効性を持ったのは、イギリス海軍(ロイヤル・ネイビー)が海上を支配していたからなのです。
イギリスもまた、中南米諸国がスペインの閉鎖的な植民地体制に戻るよりも、独立して自由な貿易相手となることを望んでいました。
つまり、初期のモンロー主義は、アメリカの独りよがりな宣言ではなく、イギリスという当時の超大国の実力に「ただ乗り」する形で成立したという側面があるのです。
私たちが「独り立ち」だと思っていた歴史の裏側には、こうした冷徹な国際政治のバランスがあったのですね。
アダムズ国務長官の知略
当初、イギリスはアメリカに対して共同で宣言を出さないかと持ちかけていました。しかし、アダムズは「イギリスのボートに繋がれた小舟になるのはごめんだ」と拒否し、あえてアメリカ単独の宣言にこだわりました。
これによって、アメリカは将来的にイギリスの影響力からも脱却する足がかりを作ったのです。このエピソードは、後の「アメリカ第一主義」の源流を見るようで、非常に興味深いものがあります。
■ 脚注解説:より深い理解のために
*3 ナポレオン戦争:19世紀初頭に欧州を席巻した戦争。この終結後、旧秩序の維持を図るウィーン体制により、中南米の再植民地化の危機が高まりました。
*4 神聖同盟:ロシア・オーストリア・プロイセンによる同盟。自由主義や独立運動を抑圧し、君主制と植民地支配の維持を図る反動的な役割を担いました。
欧州列強の介入を拒否した非植民地化の原則

モンロー主義の第一原則である「非植民地化(Non-colonization)」は、南北アメリカ大陸をヨーロッパ列強による「将来の獲物」から外すことを目的とした、非常に野心的な宣言でした。
当時の世界地図を見ればわかる通り、ラテンアメリカの多くは独立したばかりで不安定な状態にあり、ヨーロッパの目には魅力的な「空白地帯」に見えていたからです。
モンロー大統領は、「アメリカ大陸はすでに自由で独立した地位を確立しており、もはや他国の植民地化の対象にはなり得ない」とはっきり突き放しました。
この原則が及ぼした影響は多大です。第一に、中南米諸国の独立を間接的に支援する形となりました。
もちろん、アメリカが純粋に善意だけで助けたわけではありませんが、「ヨーロッパの軍隊は来るな」という警告は、独立したての小国たちにとって強力な後ろ盾に見えたはずです。
しかし、この原則にはもう一つの顔がありました。
それは、「ヨーロッパがダメなら、アメリカはどうなのか?」という問いです。
「非植民地化」は当初、民主主義と自由を象徴する言葉として受け入れられました。しかし歴史が進むにつれ、それは「アメリカ以外の国は手を出すな」という、アメリカによる地域支配の独占を意味するように変化していきました。
私たちが歴史を学ぶ際に注意すべきなのは、この原則が「アメリカ自身の拡張」を縛るものではなかったという点です。
事実、この宣言から数十年後、アメリカはメキシコと戦争を行い、テキサスやカリフォルニアなどを手に入れていきます。
つまり「非植民地化」とは、ヨーロッパに対しては厳しい制限をかける一方で、アメリカ合衆国が大陸内で影響力を拡大していくための「防壁」を築くことでもあったのです。
このダブルスタンダード*5とも取れる構造が、後にラテンアメリカ諸国との間に深い不信感を生む原因の一つにもなりました。
このあたりは、現代の「ドンロー主義」における「OUR Hemisphere(我々の半球)」という排他的な表現にも、その精神が強く引き継がれているように私には見えます。
■ 脚注解説:より深い理解のために
*5 ダブルスタンダード:二重基準。他国の拡張主義を批判しつつ、自国の拡張は正当化する矛盾を指し、アメリカ外交が「偽善」と批判される歴史的要因の一つです。
相互不干渉と分離主義が米国外交に与えた影響

「相互不干渉」と「分離主義」は、モンロー主義の最も「潔い」部分として長く語られてきました。
「アメリカはヨーロッパのことに口を出さないから、ヨーロッパもこちらに口を出さないでほしい」という、いわゆる「二つの世界論」です。
この姿勢は、独立以来のアメリカに根付いていた「孤立主義」*6を外交ドクトリンとして昇華させたものであり、その後のアメリカの外交スタイルを100年以上にわたって規定することになります。
この分離主義がもたらした具体的な影響として、アメリカが自国の開発と拡大に集中できたことが挙げられます。
19世紀のヨーロッパは、普仏戦争やクリミア戦争など、絶え間ない紛争の中にありました。もしアメリカがモンロー主義を掲げず、ヨーロッパの複雑な同盟関係に深入りしていたら、西部開拓や産業革命*7をあれほどのスピードで推し進めることは難しかったでしょう。
「余計な争いに巻き込まれない」ことが、最強の国家建設を可能にしたのです。第一次世界大戦においても、当初アメリカが参戦を渋った背景には、このモンロー主義への強いこだわりがありました。
分離主義のメリットとジレンマ:
- メリット:国内経済の発展と安定にリソースを集中できた。
- ジレンマ:国際社会が危機に瀕した際、「傍観者」でいることが許されるのかという倫理的な問いを常に突きつけられた。
しかし、この美しい「相互不干渉」の原則は、アメリカが世界最大の経済大国へと成長するにつれて、維持が困難になっていきました。
20世紀に入り、アメリカの利権が世界中に広がると、「不干渉」はもはや現実的な選択肢ではなくなったのです。
私たちが今のニュースを見ていても感じるように、アメリカが世界のどこかで起きている紛争に「全く関わらない」ことは、もはや不可能です。
むしろ、近年の動き(特に2026年のベネズエラ介入)を見ていると、アメリカは再び「西半球」という自分たちのホームグラウンドに引きこもり、そこを要塞化するために分離主義を「再定義」しているように思えてなりません。
それは、かつての「謙虚な孤立」ではなく、自国の勢力圏を絶対化するための「攻撃的な分離」へと姿を変えています。
■ 脚注解説:より深い理解のために
*6 孤立主義:他国との同盟や政治介入を避け、自国の安全と利益を最優先する姿勢。米国の建国以来の伝統であり、国内問題に集中したい時の強力な指針となります。
*7 産業革命:技術革新による生産体制の激変。米国は欧州の戦争をよそに国内市場とインフラ整備に専念し、後の超大国としての地位を不動のものにしました。
ルーズベルトの系論による国際警察力への変質
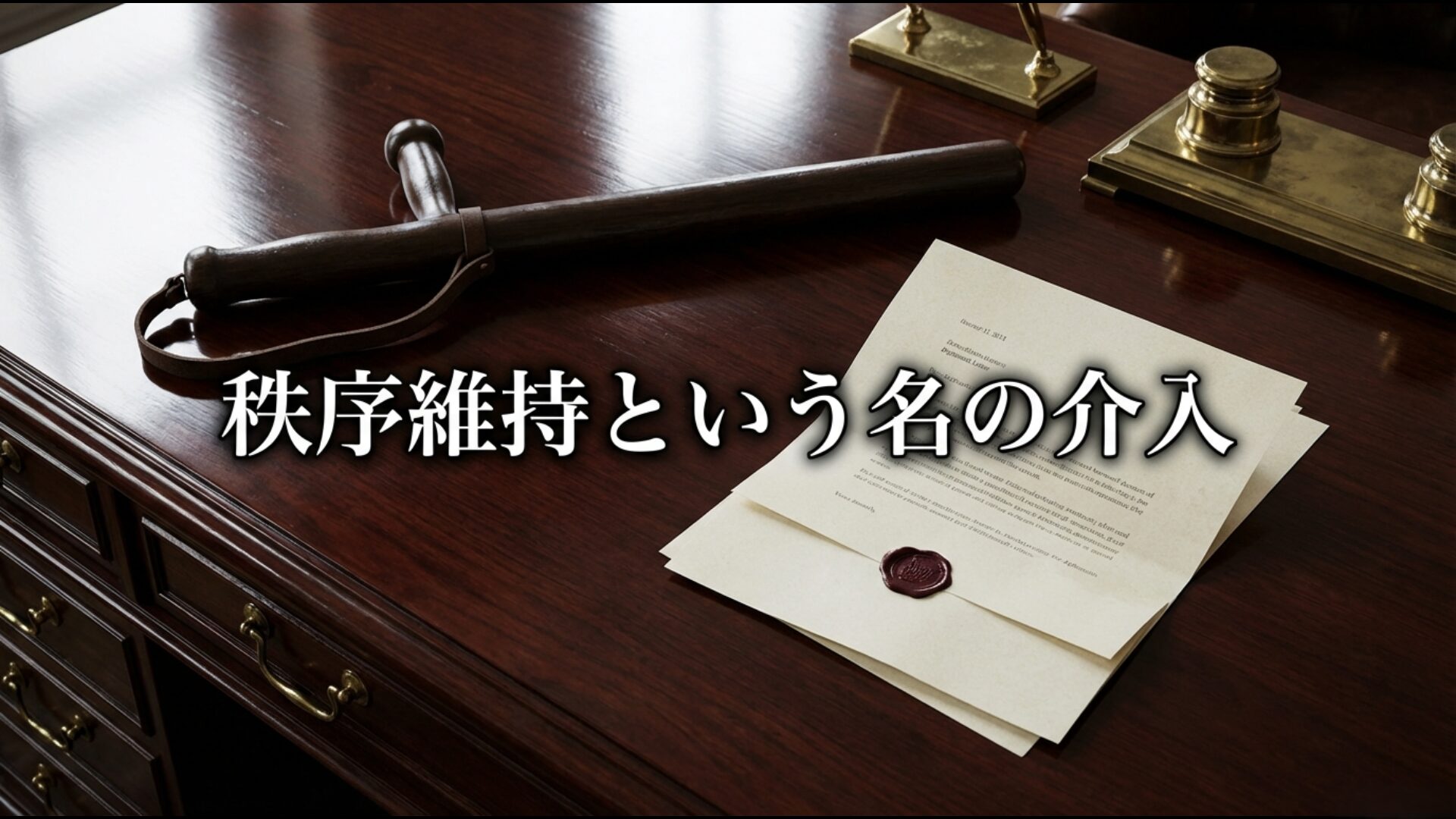
モンロー主義の歴史において、最大の転換点と言えるのが1904年に発表された「ルーズベルト・コロラリー(系論)」です。
第26代大統領セオドア・ルーズベルトは、それまでのモンロー主義に全く新しい解釈を付け加えました。
それは、中南米の国々で不祥事や混乱が起きた場合、アメリカが「国際警察力」として介入する権利があるというものです。私たちが今日、アメリカを「世界の警察官」と呼ぶことがありますが、その直接的な起源はここにあります。
ルーズベルトは、もしラテンアメリカの国々が借金を返せなくなったり、国内が内乱に陥ったりしてヨーロッパ諸国に介入の口実を与えてしまうなら、そうなる前にアメリカが先回りして治安を維持すべきだと考えました。
これは一見すると地域の安定を願う言葉のように聞こえますが、実態は「アメリカの都合で他国の主権を無視できる」という介入の免罪符でした。
この方針の下、アメリカはドミニカ共和国、ハイチ、ニカラグアといった国々に軍を派遣し、実質的な保護領化*8を進めていきました。
有名な「棍棒(こんぼう)外交(Big Stick Policy)」の時代の幕開けです。
この変質は、ラテンアメリカの人々にとって耐えがたい屈辱の始まりでもありました。アメリカは「民主主義を守るため」という名目で、実際にはアメリカ企業の利益(バナナや石油など)を守るために介入を繰り返したからです。
2026年にトランプ政権がベネズエラに介入した際、トランプ氏がこの「ルーズベルトの系論」を現代版にアップデートした「トランプ・コロラリー(ドンロー主義)」を掲げたことは、歴史を知る者にとっては背筋が凍るようなデジャヴでした。
モンロー主義が持つ、強者による「慈悲深き独裁」の側面が、100年の時を経て再び牙を剥いたのです。私たちは今、モンロー主義が「盾」でも「棍棒」でもなく、特定の目的のために振りかざされる「ハンマー」へと進化した瞬間に立ち会っているのかもしれません。
■ 脚注解説:より深い理解のために
*8 保護領化:相手国の内政や外交を条約に基づき管理下に置くこと。主権が大幅に制限され、実質的には強大国の影響下にある統治形態を指します。
冷戦期の反共主義とラテンアメリカ介入の論理

第二次世界大戦後、世界が「自由主義」と「社会主義」の二つの陣営に分かれた冷戦時代。モンロー主義は「反共主義」という新たな鎧をまとって蘇りました。
この時期、アメリカにとってのモンロー主義の目的は、もはやヨーロッパの王政を退けることではなく、ソ連の影響(共産主義)を西半球から完全に排除することへとシフトしました。
たとえ相手が民主的に選ばれた政権であっても、社会主義的な政策を掲げるなら、それは「モンロー主義への重大な脅威」とみなされたのです。
その代表例が、1954年のグアテマラでのクーデター(PBSUCCESS作戦)です。
民主的に選出されたアルベンス政権が、アメリカ企業ユナイテッド・フルーツ社の所有地を再分配しようとしたところ、アメリカはこれを「共産主義の橋頭堡」と断定し、CIA*9主導で政権を転覆させました。
また、1962年のキューバ危機は、まさにモンロー主義が核戦争の瀬戸際まで引き起こした事例です。ケネディ大統領は、ソ連によるミサイル配備を「西半球に対する敵対的な挑戦」として、断固たる海上封鎖*10を強行しました。
さらに特筆すべきは、冷戦の終結期に行われた1989年のパナマ侵攻(ジャスト・コーズ作戦)です。ブッシュ(父)大統領は、かつてCIAの協力者であったパナマのノリエガ将軍を麻薬取引の罪で起訴し、大規模な軍事介入を断行しました。
他国の元首を「法執行」の名の下に武力で拉致・連行し、米国の法廷で裁くというこの手法は、まさに現代の「ドンロー主義」の直系と言えるスタイルを確立した事件でした。
歴史を動かした介入の系譜:
- 1954年 グアテマラ:農地改革を阻止するための政権転覆。
- 1983年 グレナダ:反共を旗印にした電撃的な軍事侵攻。2026年の戦術的モデル。
- 1989年 パナマ:麻薬犯罪を理由とした他国元首の拘束。2026年の論理的モデル。
- 1980年代 ニカラグア:左派サンディニスタ政権に対する反政府ゲリラ(コントラ)支援。
これらはすべて、「裏庭に敵を入らせない」というモンロー主義のロジックが、その時々の「正義」をまとって極大化した姿と言えます。
今回の2026年のベネズエラ介入(オペレーション・アブソリュート・リゾルブ)は、1983年のグレナダ侵攻を「戦術的ひな形」とし、1989年のパナマ侵攻を「論理的ひな形」にして完成された究極の介入形態です。
冷戦が終わっても、モンロー主義の中に流れる「介入のDNA」は決して死滅していなかったのです。私たちは今、かつての「反共」が「反中・反露・反イラン」に置き換わっただけの、終わりのない歴史のループを見せられているのかもしれません。
■ 脚注解説:より深い理解のために
*9 CIA(中央情報局):米大統領直属の外交・諜報機関。冷戦下、社会主義政権の転覆やクーデター支援など、米国の国益を守るための秘密工作を世界規模で実行しました。
*10 海上封鎖:軍事力によって特定海域の交通を遮断する行為。キューバ危機ではソ連ミサイルの搬入を阻止するための「検疫」として実施され、世界を核戦争の淵に追い込みました。
ベネズエラ介入で激変したモンロー主義の目的と今後
2026年1月、私たちは歴史の教科書が書き換えられる瞬間を目の当たりにしました。それまでのモンロー主義をはるかに凌駕する、より露骨で所有権的な新ドクトリンの誕生です。
ベネズエラで何が起きたのか、そしてそれが私たちの未来にどう影を落としているのか、詳細に迫ります。
ベネズエラ介入作戦の経緯とマドゥロ大統領拘束

2026年1月3日未明(東部標準時)、カリブ海に面したベネズエラの首都カラカスは、突然の暗闇に包まれました。
アメリカ軍サイバー司令部(CYBERCOM)*11による電磁パルス攻撃とサイバー攻撃により、ベネズエラの全レーダー網と電力網が沈黙したのです。
この「真夜中のハンマー」と呼ばれた作戦は、ニコラス・マドゥロ政権を根底から揺さぶる、非情なまでの効率性をもって実行されました。
作戦の中心を担ったのは、第75レンジャー連隊やデルタフォースといった米軍屈指のエリート部隊です。彼らは最新のステルスヘリで大統領公邸「ミラフローレス宮殿」に直接降下し、わずか数十分でマドゥロ大統領とその側近、そして夫人のシリア・フロレス氏を拘束しました。
現場では「音響兵器」の使用も報告されており、警護隊員たちは抵抗する間もなく、強烈な音波による嘔吐や眩暈で無力化されたといいます。これは、従来の「戦争」の概念を飛び越えた、国家規模の「精密な誘拐」とも呼べる手法でした。
犠牲者の実態:
米軍側は「死傷者ゼロ」を強調していますが、現地の情報によればベネズエラ側には約80名の死者が出ており、その中には治安維持を支援していたキューバ軍要員32名も含まれていたとされます。この事実は、米国がキューバに対しても「次はお前たちだ」という無言の圧力をかけたことを意味しています。
拘束されたマドゥロ夫妻は、そのままニューヨーク州のスチュワート空軍基地へと移送され、現在は麻薬取締局(DEA)*12の管理下に置かれています。
トランプ政権はこれを「主権国家への侵攻」ではなく、「国際的な麻薬テロリストの逮捕状執行」という法的枠組みで処理しました。
この「軍事力を使った法執行」というスタイルこそが、21世紀における新しい介入の形として定着しようとしています。
私たちがこれまで信じてきた「国家の主権」という壁が、あまりにもあっけなく崩れ去った瞬間でした。
■ 脚注解説:より深い理解のために
*11 サイバー司令部(CYBERCOM):米軍のサイバー空間における作戦を統括する統合司令部。電力・通信網を無力化し、物理的戦闘前の優位を確立する現代戦の要です。
*12 麻薬取締局(DEA):米司法省の法執行機関。他国元首を麻薬テロリストとして訴追し、米軍による拘束に「国内法上の正当性」を付与する戦略的役割を担いました。
ドンロー主義による西半球の資源独占と石油戦略

マドゥロ政権の崩壊後、トランプ大統領が掲げたのが「ドンロー主義(Donroe Doctrine)」です。これは単なる言葉遊びではありません。
モンロー主義が掲げていた「勢力圏」という抽象的な表現を、「所有領域」という露骨な言葉に置き換えたものです。その最大のターゲットは、ベネズエラの地中深くに眠る、世界最大の石油埋蔵量(約3,000億バレル)に他なりません。
トランプ氏は介入直後、「ベネズエラの石油は今や米国の管理下にある」と公言しました。これには経済的な計算も働いています。
ベネズエラ産原油は、精製が難しい「超重質油」ですが、実はアメリカのメキシコ湾岸にある最新の製油所は、この原油を最も効率よくガソリンや製品に変えられるように設計されています。
つまり、ベネズエラの石油を掌握することは、アメリカのエネルギー産業にとって「失われた最後のパズル」を手に入れることに等しいのです。
さらに、ドンロー主義は「資源ナショナリズム」*13の逆転を目指しています。
リチウムやレアアースなど、次世代の産業に不可欠な資源が豊富な中南米において、アメリカ以外の国(特に中国)に利権を渡さないという宣言です。
レアアースについては、別記事「レアアースはどこで取れる?日本の深海に眠る宝の山と中国依存の正体」も参考としてください。
これはもはや外交政策ではなく、巨大な「ビジネス・ディール」そのものです。私たちが普段使っているエネルギーやスマートフォンの裏側に、こうした血なまぐさい覇権争いが直結しているという事実は、非常に重い現実としてのしかかってきます。
正確な経済的影響については、今後の市場動向やエネルギー専門家の分析を待つ必要がありますが、世界的な供給網*14が激変していることだけは確かです。
■ 脚注解説:より深い理解のために
*13 資源ナショナリズム:自国の天然資源に対する権利を強め、国家が管理・開発を主導する動き。ドンロー主義はこれを米国主導で再編しようとする試みです。
*14 供給網(サプライチェーン):原料調達から製品が届くまでの一連の流れ。供給元を掌握されることは、他国の先端産業の生死を握られることに等しい重要性を持ちます。
グリーンランド買収への圧力と北極圏の軍事化

ドンロー主義が牙を剥いたのは、熱帯のベネズエラだけではありませんでした。
トランプ大統領の視線は、北極圏に浮かぶ巨大な島、デンマーク領グリーンランドにも向けられています。
2026年に入り、トランプ大統領はグリーンランドを「米国の国家安全保障にとって不可欠なピース」と断定し、デンマーク政府に対して「買収」か「実力行使を含めた圧力」かという、極めて厳しい二者択一を迫っています。
これには、北極海航路の支配権を争うロシアや、レアアース資源を狙う中国を完全に封じ込めるという、冷徹な計算が働いています。
グリーンランドは、北極海の入り口に位置し、ロシアの潜水艦やミサイルを監視するための「GIUKギャップ(グリーンランド、アイスランド、イギリスを結ぶ海域)」の延長線上にあります。
軍事的な拠点としての価値はもちろんですが、温暖化によって氷が解け始めたことで、そこには莫大なレアアースや貴金属が眠っていることが判明しました。
トランプ大統領は、これらを中国のサプライチェーンから切り離し、アメリカの所有物にすることを目論んでいます。
デンマークはNATO*15の創設メンバーであり同盟国ですが、トランプ氏は「同盟国だからこそ、アメリカの安全のために譲歩すべきだ」という、これまでの国際常識では考えられない論理を展開しています。
まさに北極から南極までを「我々の半球」とする、ドンロー主義の恐ろしさを象徴する出来事と言えるでしょう。
■ 脚注解説:より深い理解のために
*15 NATO(北大西洋条約機構):欧州・北米諸国の集団安全保障体制。加盟国への強引な割譲要求は同盟の相互信頼を破壊し、内部崩壊を招く深刻なリスクを伴います。
国際法の形骸化と中露を含む各国からの反発
ベネズエラへの軍事介入とマドゥロ大統領の拘束は、国際法の世界に「主権免除」*16の崩壊という巨大な地殻変動を引き起こしました。
これまで、たとえ独裁者であっても一国の元首を他国が直接拘束することは、国際法上の主権侵害とみなされてきました。
しかし、トランプ政権はこれを「ナルコテロリズム(麻薬テロ)」という米国内法の枠組みで強行し、「テロリストに主権など存在しない」という論理で世界を押し切ろうとしています。
当然ながら、これに対してロシアや中国は猛烈な非難を浴びせています。しかし、ベネズエラでの圧倒的な米軍の展開能力、および最近の「幽霊船団(ロシアの制裁逃れタンカー)」の拿捕といった実力の行使を前に、彼らもまた有効な手立てを失っているのが実情です。
むしろ、中露がこの米国の行動を、他国への介入を正当化する「前例」として悪用するリスクを専門家は懸念しています。
国際社会が抱く懸念の所在:
- 「麻薬テロリスト」と定義すれば、他国元首をいつでも拘束できるという危険な前例。
- 国連安保理*17の機能不全が加速し、多国間協調が完全に死に体となるリスク。
- アメリカと中露による「勢力圏」の奪い合いが激化し、中小国の主権が犠牲になること。
欧州連合(EU)の指導者たちも、この「予測不可能な同盟国」に対して強い警戒感を抱いています。
かつてはアメリカを自由民主主義の守護者と仰いでいましたが、ドンロー主義の下で動く現在のアメリカは、自国の国益のためなら同盟国の懸念すら一蹴する存在になっています。
私たちがこれから生きていく世界は、法のルールよりも「誰が一番強いか」がすべてを決める、極めて不安定な場所になってしまうのかもしれません。世界が再び「パンドラの箱」を開けてしまったことは間違いなさそうです。
■ 脚注解説:より深い理解のために
*16 主権免除:一国の裁判権が他国の元首や公的行為に及ばないとする国際慣習法。この崩壊は大国が実力で他国主権を否定する「裸の力の時代」への回帰を示唆します。
*17 国連安保理(安全保障理事会):世界の平和と安全に責任を持つ機関。大国の対立による麻痺は国際的な「法の支配」が消滅した無法状態への扉を開くことになります。
米国内の戦争権限法を巡る憲法危機と政治的対立
ベネズエラ介入は、アメリカ国内においても深刻な亀裂を生んでいます。
事の発端は、トランプ政権が今回の「オペレーション・アブソリュート・リゾルブ」を実行する際、法的に義務付けられている議会指導部への事前通告、いわゆる「8人組(Gang of Eight)」への報告を一切行わなかったことです。
ホワイトハウスは「情報漏洩のリスクを避けるため」と説明していますが、これは憲法が定める議会の監督権限*18を真っ向から否定する行為であり、アメリカ政治の根幹を揺るがす事態となっています。
上院では、民主党のティム・ケイン議員らが中心となり、大統領の独断による軍事行動を厳格に制限する決議案が提出されました。驚くべきは、党利党略を超えて、共和党の一部議員までもがこの動きに同調し、造反の動きを見せていることです。
これに対しトランプ大統領は、自身のSNSでこれらの議員を「恥を知れ」と名指しで批判し、さらに「戦争権限法そのものが違憲である」という、これまでの大統領が踏み込まなかった領域にまで踏み込みました。
この対立は、アメリカが「法の支配に基づく民主国家」であり続けるのか、それとも「強力な指導者による帝国」へと変貌するのかを問う、憲法上の大決戦となっています。
行政府*19と立法府の間の対立が激化する中、アメリカが内部から崩れていかないか、その行く末を冷静に見守る必要があります。
■ 脚注解説:より深い理解のために
*18 監督権限:議会が政府の活動をチェックし権力暴走を防ぐ憲法上の権利。軍事行使における承認権限は民主主義の生命線であり、これの否定は独裁への近道と危惧されます。
*19 行政府:大統領を長とする法律執行・行政運営機関。チェック・アンド・バランスの崩壊は、三権分立という近代民主主義の根幹が死文化することを意味します。
日本を含む国際社会への波及効果と将来の懸念
さて、一見すると遠い南米や北極圏の話に思える「ドンロー主義」ですが、私たち日本にとっても決して他人事ではありません。
アメリカが西半球を「自分たちの要塞」として再編し、そこにリソースを集中させ始めたことは、アジア太平洋地域におけるアメリカの影響力が相対的に低下する可能性を示唆しているからです。
日本は長年、日米同盟を安全保障の基軸としてきました(外務省:日米安全保障体制)が、トランプ政権の「西半球優先主義」の下で、これまで通りの支援や関与が維持されるのかという不安が現実のものとなっています。
特に経済面での影響は甚大です。ベネズエラの石油がアメリカの管理下に置かれたことで、世界のエネルギー価格は一時的に変動していますが、長期的には「アメリカ以外の国へのエネルギー供給」が制限されるリスクがあります。
日本のような資源輸入国にとって、エネルギー源の多角化は死活問題です。もしアメリカが自国の石油メジャーの利益を優先し、日本への供給や第三国との取引に制限をかけるような事態になれば、私たちの生活コストや産業競争力に直撃します。(参考:経済産業省 資源エネルギー庁(日本のエネルギー 2024年度版)
こうした中、日本政府にはこれまでにない極高度な外交手腕が求められています。
アメリカとの良好な関係を維持しつつも、過度な依存を避け、独自に資源国とのパイプを強化する。あるいは、国際社会において再び「法の支配」の重要性を説き続け、孤立化するアメリカを繋ぎ止める役割です。
■ 脚注解説:より深い理解のために
*20 抑止力:相手に攻撃を思いとどまらせるための力。米国のプレゼンス低下は地域のパワーバランスを崩し、不安定化を招く大きな要因となります。
よくある質問(FAQ)
なぜ2026年の新ドクトリンは「ドンロー主義」と呼ばれているのですか?
ANSWER 第47代ドナルド・トランプ(Donald Trump)大統領の名と、1823年のモンロー(Monroe)主義を掛け合わせた造語です。従来のモンロー主義が他国の介入を防ぐ「盾」であったのに対し、ドンロー主義は西半球をアメリカの「所有領域(OUR Hemisphere)」と定義し、資源独占や直接的な政権交代を辞さないより攻撃的な「覇権維持システム」への昇華を意味しています。
ベネズエラ介入は国際法違反ではないのですか?
ANSWER 従来の国際法における「主権免除」の原則に照らせば、他国元首の拘束は主権侵害にあたります。しかし、トランプ政権はマドゥロ氏を「一国の指導者」ではなく「国際的な麻薬テロリスト(ナルコテロリズム)」と定義し、米国内の逮捕状を執行するという「法執行(Law Enforcement)」の枠組みを適用しました。これにより軍事行動を「警察権の行使」として正当化しており、法の解釈そのものを力の論理で書き換えている状況です。
ドンロー主義が日本企業や家計に与える具体的なリスクは何ですか?
ANSWER 主なリスクは「エネルギーコストの不透明化」と「アジアにおける抑止力の低下」です。アメリカがベネズエラ石油を独占管理下に置くことで、世界的な原油供給バランスが米国の戦略一つで左右されるようになります。また、アメリカが「西半球(裏庭)」の要塞化にリソースを集中させることで、相対的に東アジアへの関与が減り、地政学的リスクが高まる可能性があります。これは日本国内の株価や防衛関連予算の増大という形で、将来的に家計に波及する懸念があります。
中国やロシアがこの動きを「前例」として悪用する可能性はありますか?
ANSWER 極めて高いと言わざるを得ません。米国が「自国の安全保障と法執行」を理由に他国元首を拘束したことは、他国が周辺地域に介入する際の強力な「ロジックのひな形」になり得ます。例えば、中国が台湾周辺で、あるいはロシアが周辺国で同様の「法執行」を名目に軍事介入を正当化するリスクが生じており、国際秩序が「ルールに基づく対話」から「実力による既成事実化」へと大きくシフトする危険性(パンドラの箱)が指摘されています。
今後、モンロー主義がかつての「防衛的」な姿に戻ることはありますか?
ANSWER 現在の多極化する世界情勢を鑑みると、19世紀のような受動的な「孤立主義」に戻ることは極めて困難と考えられます。資源の争奪戦やサイバー空間での対立が常態化する現代において、「何もしないこと」は他国の影響力を許容することを意味するからです。米国内の政権交代によってトーンが和らぐ可能性はあっても、西半球を自国の生命線とみなす戦略的価値自体は、今後も不変の外交基軸であり続けるでしょう。
現代社会で問い直されるモンロー主義の真の目的

200年前、ジェームズ・モンローが提唱した「モンロー主義」は、アメリカという若い国家が、自分たちの自由と平和を守るために築いた「盾」でした。
しかし、私たちが今回の2026年ベネズエラ介入事件を通じて目撃したのは、その盾が完全に作り直され、他国の主権や世界の資源を掌握するための強力な「ハンマー」へと進化した姿です。
モンロー主義の目的が、防衛から支配へとこれほどまでに鮮やかに変容してしまった現実に、私は深い感慨と危機感を覚えずにはいられません。
歴史を振り返れば、あらゆるドクトリンは時代とともにその色を変えてきました。今回の「ドンロー主義」がこれまでのものと決定的に異なるのは、国際的なルールという枠組みを、公然と「不要なもの」として切り捨ててしまった点にあります。
これは、第二次世界大戦後に築き上げられてきたリベラルな国際秩序そのものへの挑戦です。力がすべてを解決し、勝者が資源を総取りする——。そんな「裸の力の時代」に、私たちは再び足を踏み入れました。
本記事のまとめ:ポイントは以下の3点です
- ✓
モンロー主義の目的は、1823年の「防衛」から2026年の「資源独占と覇権の絶対化」へと変容した。 - ✓
ベネズエラ介入は、国際法の形骸化と同盟関係の再編を象徴する歴史的な出来事である。 - ✓
日本を含む国際社会は、アメリカの「西半球集中」に伴う地政学的・経済的リスクに備える必要がある。
この記事が、皆さまにとって世界の明日を考える一つの材料となれば幸いです。
本記事は2026年1月時点の公開情報に基づき、地政学リスクおよび経済情勢を分析したものです。軍事介入に伴う国際法上の解釈やエネルギー市場の価格変動、各国の外交政策には高い不確実性が含まれており、事態の推移によって内容の正確性が変化する可能性があります。個別の投資判断や法的・外交的対応については、必ず公的機関の最新情報や専門家の見解を確認し、自己責任において判断してください。
- ✓1823年提唱の本来の目的は米国の生存戦略
- ✓列強介入を防ぐ盾としての非植民地化等の原則
- ✓ルーズベルトの系論により積極的介入の棍棒へ
- ✓冷戦期は反共主義を掲げラテンアメリカへ介入
- ✓2026年ベネズエラ介入の背後には石油資源独占
- ✓ドンロー主義は西半球を米国の所有領域と定義
- ✓国際法の形骸化や中露の反発を招く深刻な懸念
- ✓米国内でも戦争権限法を巡り憲法危機が露呈
- ✓日本のエネルギー供給網や抑止力にも影響波及
- ✓現代のモンロー主義は支配を強めるハンマー


